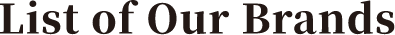20世紀末、日本中が赤ワインブームに沸き、ぶどうは異常な高値で取引された。
「ぶどうをどんどん作ってくれ!」というメーカーの要請で、農家は果物の栽培を縮小してまでワイン用のぶどうを苗から増やしていった。
ところが3年後、ようやく収穫できるようになった頃。
ワインブームに陰りが見え始め、収穫された大量のぶどうが農家のもとに残った。
引き取り手は日本中どこにもなかった。
「なんとか、ぶどうを引き取ってもらえないだろうか」。
私たちのもとに多くの農家が訪ねてきた。
私たちもブームを見込んで収穫量を増やしていたことから、すでに飽和状態だった。
しかし思い悩んだ末、引き取る決断をした。
日本全国から日本酒用の中古タンクをかき集め、不眠不休で仕込みを続けた。
結局この年に仕込んだワインを完売するまで3年かかった。
しかし私たちは思いもしなかった大きな収穫を得た。
この出来事をきっかけに、多くの農家の方々が私たちと取引をしたいと申し出てくれるようになった。
最大の危機が強い絆を結んでくれたのだ。
ヴィンヤードの紹介はこちら